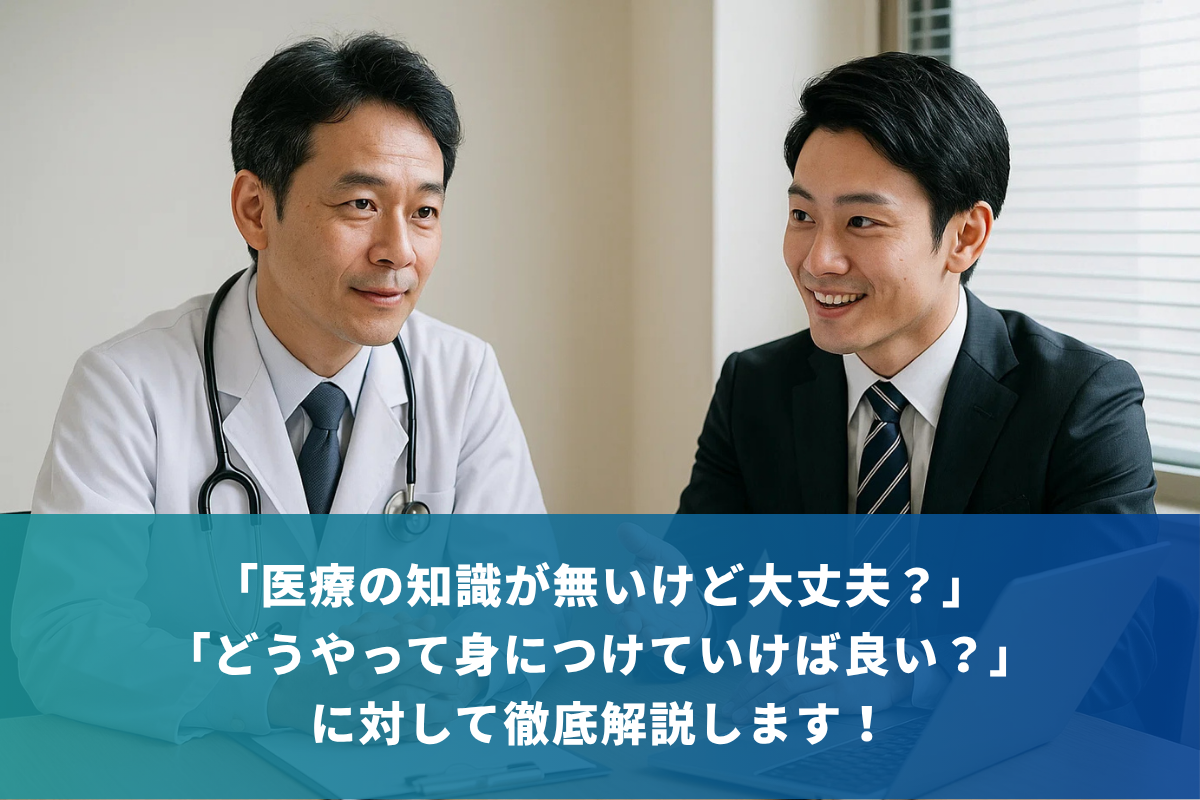
採用活動をしていると、多くの応募者の方から
「医療関係の知識が無いのですが大丈夫でしょうか?」
「どうやって医療関係の知識を身につければ良いですか?」
といった質問をよくいただきます。
しっかりとご回答したいところなのですが、面接の場では限られた時間の中でお答えするため、なかなか十分にお伝えできません。
そこで、今回はブログ記事として、弊社の業務において、どのような医療的知識が必要とされるのか?また、どのように身につけるべきなのかをお伝えいたします。
完璧な医療知識を持つ人は、ほぼいません
正直に言えば、弊社のメンバーで「医療関係の知識は完璧です」と言える人はいません。
おそらく全国を探しても、そんな人はほぼいないでしょう。
なぜなら、医療という分野は非常に幅広く奥深いからです。
一口に医療といっても、歯科・内科・眼科・整形外科・精神科など、診療科は多岐にわたり、それぞれの専門家が日々研鑽を積んでいるような領域なのです。
マーケティングに必要な医療知識とは
私たちのように医療機関のマーケティングを担う会社で活躍するために必要なのは、全てを深く学ぶことではありません。
「各分野の表層を正しくとらえ、マーケティングに必要な情報を理解すること」です。
例えば、次のような知識が役立ちます。
- 各診療科の患者さんの悩みと主な診療内容
- 保険診療と自費診療の違い、および収益性の高い自費診療
- クリニック経営の基礎知識
- 開業までの流れと資金計画
- 医療従事者の採用に関する知識
各診療科の患者さんの悩みと主な診療内容

医療機関は診療科ごとに患者層や抱える悩みが異なります。
たとえば歯科では「虫歯や歯周病による痛み」「歯並びや見た目の悩み」「入れ歯の不具合」などが多く、診療内容は保険内の虫歯治療や歯石除去から、自費のインプラントや矯正まで幅広く行われます。整形外科は腰痛や関節痛、骨折、スポーツ障害など身体機能の回復を目的とし、リハビリを含めた長期通院が特徴です。
医療機関のお客様の広告をお任せいただくには、それぞれの診療科で患者が最も不安に感じているポイントや来院動機を理解することが大切です。
保険診療と自費診療の違い、および収益性の高い自費診療
日本の医療制度における保険診療は、公的医療保険の適用を受け、患者が原則3割(年齢や所得により変動)を負担し、残りを国や自治体が負担します。内容や価格は国が定めた診療報酬に基づくため、患者負担は少なく、提供する医療も標準化されていますが、医療機関側から見ると単価は低く、件数を増やさなければ収益を伸ばしにくい構造です。
一方の自費診療(自由診療)は保険適用外のため、医療機関が価格や内容を自由に設定できます。美容医療(シミ取り、脱毛、ボトックス)、歯科のインプラントや矯正、がんドック、先進医療などが代表例です。自費診療は1件あたりの単価が高く、収益性が高いことが特徴ですが、保険診療と異なり「患者に選ばれる理由づくり」が重要です。例えば歯科インプラントなら症例数や実績、保証制度の明確化が集患の鍵となります。
お客様のご支援をするにあたり、保険と自費の違い、どこまでが保険適用でどこからが自費なのかを理解しておく必要があるのです。
クリニック経営の基礎知識

クリニック経営の経営についての理解も必要になります。
とはいえ、基本は「売上=患者数×単価」というシンプルな考え方です。これに、診療報酬制度(保険で決まっている料金)、診療時間、スタッフの人数や配置などの条件が影響します。
経営を支えるポイントは大きく4つあります。
1つ目は集患。立地や広告、口コミによって患者さんが来てくれる環境をつくります。
2つ目は収益管理。保険診療と自費診療のバランスを見直し、単価を上げたり診療効率を高めたりします。
3つ目は人材確保。スタッフが辞めない環境を整えることが重要で、採用や教育にも力を入れます。
4つ目は業務効率化。電子カルテや予約システムの導入で待ち時間を減らし、回転率を上げます。
当然、わたしたちWebマーケティングの会社に求められるのは、主には1つめの集患の部分になります。
開業までの流れとWeb周りの準備
クリニックの開業は、先生によって考え始めるタイミングが異なります。多くは勤務医として経験を積み、開業したい地域や診療スタイルが固まった頃に「自分の理想の医療を提供したい」と考え始めます。特に30代後半〜40代は開業を意識する方が多く、資金面や家族のライフステージも大きな判断要素になります。また、親御さんのクリニックを継承するケースや、結婚を機に新規開業するケースもあります。
ホームページ業者が関わるのは、実は開業準備の比較的早い段階です。物件や内装が固まり、開業日が決まる前後から動き出せれば、集患戦略を計画的に進められます。この時期に関わることで、診療科や地域特性、先生の診療方針を踏まえたコンセプト設計が可能になります。また、内覧会や開業告知のための広告・SNS施策とホームページ制作を連動させることで、初月からの来院数に直結します。
医療従事者の採用に関する知識

クリニック経営において、医療従事者の採用は最重要課題のひとつです。
対象は医師、看護師、歯科衛生士、受付・医療事務、放射線技師など職種ごとに異なり、必要な資格や経験、業務範囲も大きく異なります。採用市場では慢性的な人材不足が続き、特に看護師や歯科衛生士は競争率が高い状況です。採用成功のためには、給与や待遇だけでなく、働きやすい職場環境の整備が不可欠です。勤務時間の柔軟性、研修制度、チームワークの良さ、院長の人柄などが定着率を左右します。採用手法は求人媒体、ハローワーク、人材紹介会社、SNS活用などがあり、それぞれ費用や効果が異なります。面接ではスキルだけでなく患者対応力や協調性を見極めることが大切です。また、採用後の教育体制も重要で、マニュアルやOJTの整備により早期戦力化と定着を促進します。採用は単発のイベントではなく、常に優秀な人材との接点を持ち続ける「継続的な採用活動」が成功の鍵です。
効率的な学び方
医療の世界を網羅的かつ体系的に学ぶための完全な方法は、正直ありません。
しかし、実務を通して効率的に知識を深めることは可能です。
1. 「わからない」をその日のうちに解決する
打ち合わせの中で知らない言葉が出てきたら、必ずメモし、その日のうちに調べます。
私はその場で「勉強不足で申し訳ありません」と前置きして質問しますが、これが原因で怒られたり、馬鹿にされたことは一度もありません。
2. 担当分野を徹底的に調べる
たとえば地方都市で新規開業する眼科を担当する場合、その地域の眼科クリニックを細部まで調査します。
また、その先生が提供する治療メニューについては、自分の言葉で説明できるレベルまで理解します。
(なぜなら、その広告を任されているからです)
3. 書籍やSNSでのインプット
場当たり的な学びだけでなく、日頃からインプットする方法も有効です。
特におすすめなのは、各診療科の先生が自らのクリニック経営について書いた本。
開業から患者さんを増やすまでのプロセスや工夫を、リアルな事例として学べます。
社内の学習環境
弊社では定期的に社内勉強会を行い、過去の勉強会は動画でいつでも視聴可能です。
テーマ例:
- 「インプラントとは?」
- 「乾癬ってなんだろう?」
- 「職種別仕事内容と働き方」
医療未経験からでも活躍できる
弊社で働くメンバーの多くは、医療とは全く関係のない業界からの転職です。
医療は簡単な分野ではありませんが、入社後に知識を身につけることができます。
医療知識ゼロからのスタートでも、学び続ける姿勢があれば必ず成長できます。
安心してチャレンジしてください。








